3年理科 「探れ!同じもの しんけいすいじゃく」②(ものの重さ)
公開日: 2025年9月21日日曜日 3年
第2回は、1時間目の導入~中盤までの様子をお伝えします。
本単元の教材についてはこちらです。
https://rika-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2025/09/3.html
前回、中の見えないカップを使って実践するとお伝えしましたが、実は、授業の導入からは扱いません。
それは、まず子どもたちと「重さ」の世界にひたり始める時間が必要だからです。
きっと前週まで「音のひみつ」の授業をしてきた子どもたちに中の見えない紙コップを渡したら、紙コップを振って、音で特定しようとする子どもが多くなるでしょう(直前の2時間は36人みんなでつながる糸電話を目指す、紙コップを使った糸電話大作戦を行っています)。
そこで、まずは身の回りの重さについて子どもたち同士の認識を比べ合うことから始めました。
身の周りで重いものは?と問うとテレビや机などが挙がりました。逆に軽いものは?と問うと紙や鉛筆などが挙がりました。
これらは、それぞれ一般論として日常で重い・軽いと認識されてるものが挙がっています。同時に、重い物を持ったとき、手にグッという感じがすることも確認しました。
その上で、子どもたちに自分の筆箱の中から1つ文房具を選んでもらい、重さ比べをすることにしました。
①まずは手に持たず、見た目で重さの順を予想します。
②次に、手で持ち比べて自分の予想が当たっていたかを確認します。
一旦みんなでどうだったかを確認しました。
C:だいたい予想と合っていました。○○さんのはさみが一番重かったです。
C:○○さんの消しゴムと、○○さんのペンの重さが一緒でした。
C:○○さんの鉛筆と○○さんの定規は重さが似ていてよく分かりませんでした。
C:はかれるものがあれば、比べられるんじゃない?
重さを実感する時間をとった上で、数値化して調べたいという思いを取り上げ、はかりを子どもたちに渡しました。今回の実践で用いるのは電子てんびんです。
すると、「同じだと思っていたけど、3g重さが違った」などの気付きがあり、重さを数値化する良さに気付いていきました。
ここで話題にしている重い・軽いは、先ほどのものと違い相対的なものであり、例えば一般的にはあまり重いものとして認識されない”はさみ”も、”鉛筆”や”消しゴム”と比べたときには重いものとなるのです。本単元の学習ではこちらの捉え方で重さを活用していきます。
そしてこれらの活動を経て、1時間目の後半、子どもたちに5つの紙コップを提示しました。
子どもたちは、まずどのように反応するでしょうか。
次回に続きます。https://rika-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2025/09/3_36.html
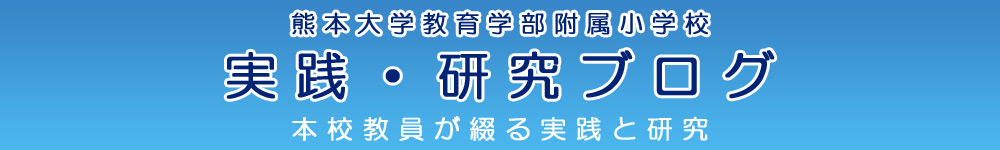












0 件のコメント :
コメントを投稿