3年理科 「探れ!同じもの しんけいすいじゃく」④(ものの重さ)
公開日: 2025年9月22日月曜日 3年
第3回は、2時間目の後半~3時間目後半までの様子をお伝えします。 本単元の教材についてはこちらです。https://rika-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2025/09/3.html
前回の様子はこちらです。
少しずつ中の粒の違いが分かってきた子どもたち。
しかし、まだカップごとの重さを電子てんびんで量った班は一部でした。
そこで2時間目の後半はア~オの重さを量ることにしました。[2時間目ここまで]
そして3時間目の初めに『体積』という言葉をおさえた上で結果を整理すると、以下の表のようになりました。
これはなぜかな?と問いかけると、すぐに「誤差」だと数人の子どもから答えがありました。
「誤差って何?」と問い返すと、「ちょっとした差」であるとか「はかりのどこに置いたかとか、どのタイミングで読み取ったか(デジタルなので表示が50…51,50,51…,50…と表示が変わり続けることもある)」というように、自分の言葉で説明することができました。
本実践においては、差をまったく出さないということよりも、差は出るものという前提で、「なぜ差が出てしまったか」をその状況に応じて考える方針で考えています。
ここでは、
「イ・ウは同じ重さなのにイの方が少ないということは、イの方が粒が重いのではないか」
「エは量が多い(体積が大きい)のに、重さが一番重い。エはこの粒自体が軽いのではないか」という考えがだされました。
また、考察の中で出た、「同じ大きさ(体積)なのに重さが違うものがあるか試してみたい」という、わかこさんの思いを取り上げると、しょうさんが「例えば木と鉄では鉄が重い」というように、生活経験に結び付けて考えだしました。
そこで、問題「同じ体積でも、ものの種類を変えれば、重さは違うのか」を立ち上げ、確かめ方を伝えました。
木や鉄は、同じ体積に揃えることが難しいので、質量比較用のブロックを用います。
すると、結果は以下のようになりました。
子どもたちは「木は少し削れているものがあった?」とか「鉄はさび具合が少しずつ違った」というように、重さの違いは認識しつつ、”だいたい同じ”ということには納得しているようです。
この結果から分かったことをまとめると、全体では、
「同じ体積でも、ものの種類が違うと、重さも違う」となりました。
しかし、しょうくんは「同じ種類なら、、、」という書き出しでまとめていました。
そこで、これを取り上げ、この書き出しでも言えそう?と全体に問いました。
授業の最後には「同じ種類なら、体積は変わらない限り、重さは同じ」というしょうくんなりのまとめを全体に発表してもらいました。が、分かった子どももいれば、よく分からないなあという表情の子どももいます。
「同じ体積でも、ものの種類が違うと、重さも違う」と「同じ種類なら、体積は変わらない限り、重さは同じ」は、同じようなことを言っているのですが、”違いで分ける””同じでまとめる”という逆の考え方をしています。
しかし、どちらとも大切な考え方です。特に後者は、小学校5年生算数の「単位量あたり」の考え方を経て中学1年生で学習する「密度」につながるものです。
次の授業に続きます。
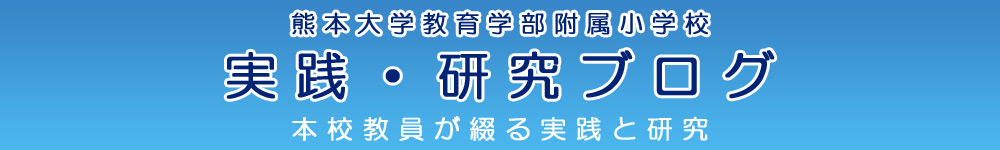















0 件のコメント :
コメントを投稿